言葉を教えていないからこそ、“わけ”を考える
名古屋でグループホームを立ち上げたときに、新卒ばかりの6人で1ユニットやってみたんですね。リーダーも置かないで。
その新卒6人の中で、介護のことを勉強してる子は1人しかいません。
周りからは「そんな無謀な」と思われましたが、実験としてやってみたんです。
認知症の方にかかわるのは、僕の友人のグループホームで2日間だけ。
まず前提として、「基本的に認知症のことを一切教えない」、「世の中に出回っている言葉、いわゆる”専門用語”を絶対教えない」状態で始めました。
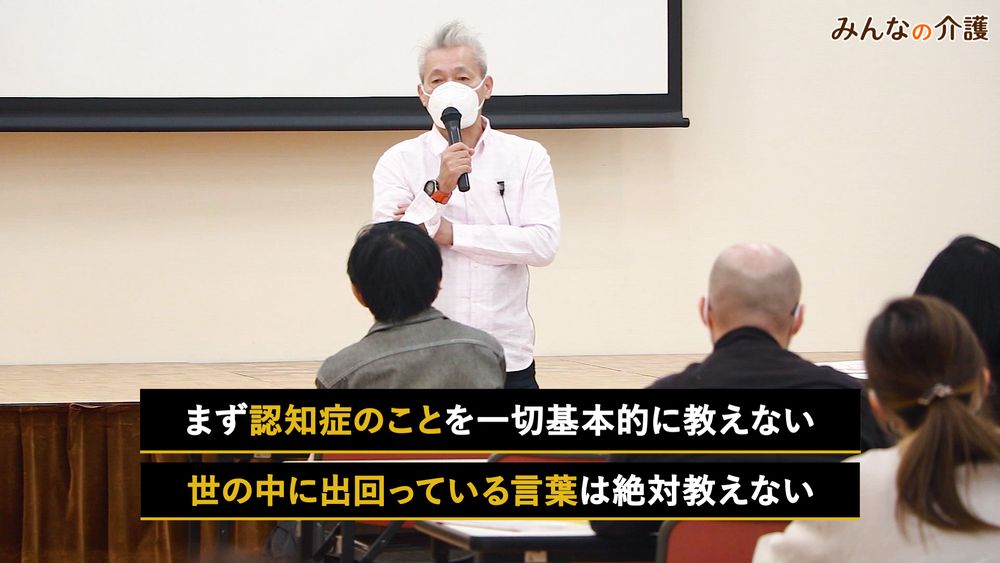
実際にやってみるとわかったことがいくつかあったんですが、その1つが日誌に記されていました。
日誌を読むと、「Aさんが夜中に廊下を“巡回”されていました」って書いてあるんです。
皆さんなら“徘徊”って書きません?
徘徊って言葉を教えていないんで、”巡回”になるんですよ。
さらに素敵だったのが、彼らはそこから「なぜAさんはこんな夜中に巡回したんだろう?」って考えたそうなんです。
「きっとAさんは目が覚めたときが朝で、何か他人様のお部屋を開けながら探してたんじゃないか」と推察していたんですね。
これがもし徘徊だったら、「徘徊という症状が出ている」という判断で考えが止まってしまいます。
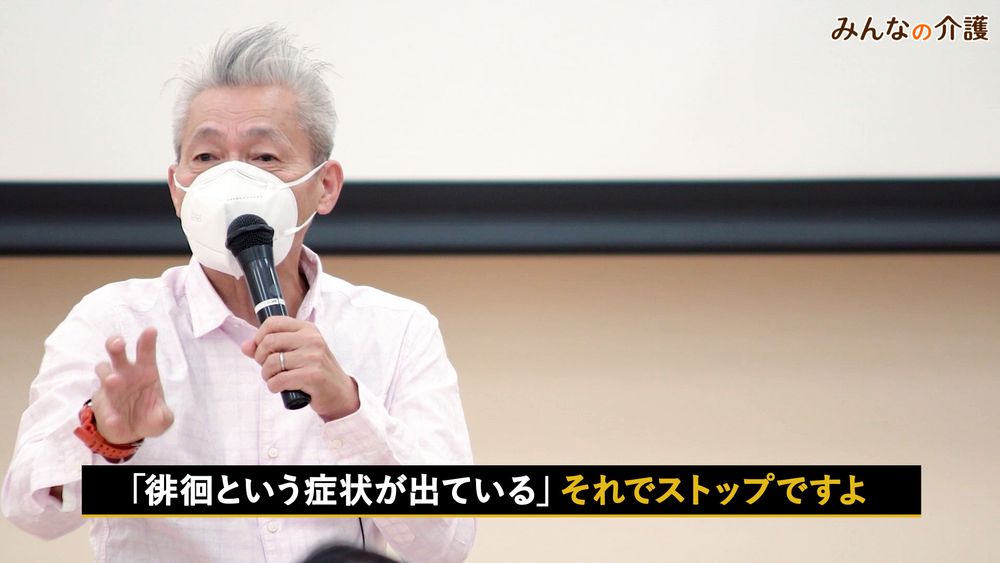
「何で徘徊してるんだろうね?」という疑問に対して、「脳の病気だからだよ」と結論づける。これで終わりですよ。
決まり事ではない“知恵”を仕事の中で生かす
もう1つ面白かったのは、「決まり事」について。
僕は新卒の子たちに「決まり事で動くな」「必要なことを思い描いて動いてくれ」と伝えていたんですね。
そしたら、「ちゃんと決まり事をつくる」んですよ。
「A勤は何をして、B勤は何をして…」って。
一切つくるなって言ったんですよ。「気づきでやれ」って言ったのに、ちゃんとつくるんですよ。
一人の子に理由を聞いてみたら「漏れがないように」って言うんですよ。
そんなこと言われて、皆さんは信じますか?
僕はその子にこう伝えました。
6人の中でやる人とやらない人が出てきたんだろう。皆の中に「あの人は何もしない」というのがあるんだろう。
だから、やる人とやらない人に分かれないように、必ずやること、決まり事をつくったんだろう。
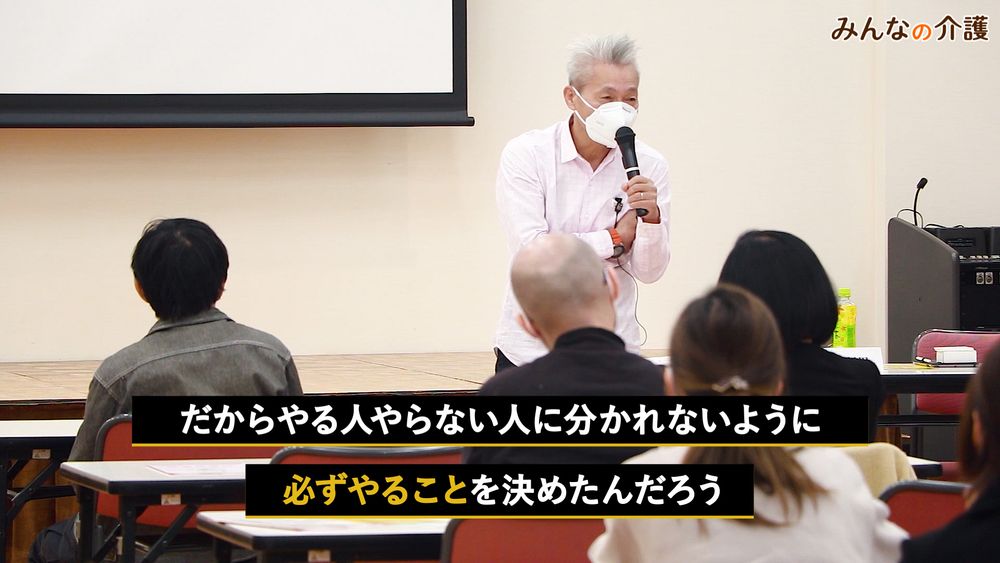
それは「知恵」だよな。
僕は「決まり事をつくるなよ」って言ったけれども、そうしないと6人の新卒者たちで円滑に組織運営ができないから、和田さんに逆らって自分たちで決まり事をつくったんだよな。
それは、素敵な知恵だよな。
…っていう話をしたんです。
新卒の子たちとのやり取りを通して改めて思いましたが、人間にはやっぱり知恵がありますね。
この子たちみたいに、知恵が仕事の中で生かせるような職場にしたいですよね。
決まり事じゃなくて知恵。そうすることが、プロの介護職が本来求められる、クリエイティブな介護につながっていくと思うんです。




