暮らしの姿を変えるのは、能力の変化ではなく「環境の変化」
新型コロナウイルスは、皆さんの暮らしの姿を変えたのではないでしょうか。
いつもの買いものに行かなくなったり、夜な夜な飲み歩いていた人が飲み歩かなくなったり、電車に乗ることを控えたり。
新型コロナが暮らしを今までとは違う姿に変えたと思うんです。
これは皆さんの能力が変わったわけではなくて、皆さんの環境の変化によって起こりました。
実は、認知症の方も同じで、どんな環境の中に行くかで「生きる姿」が変わります。
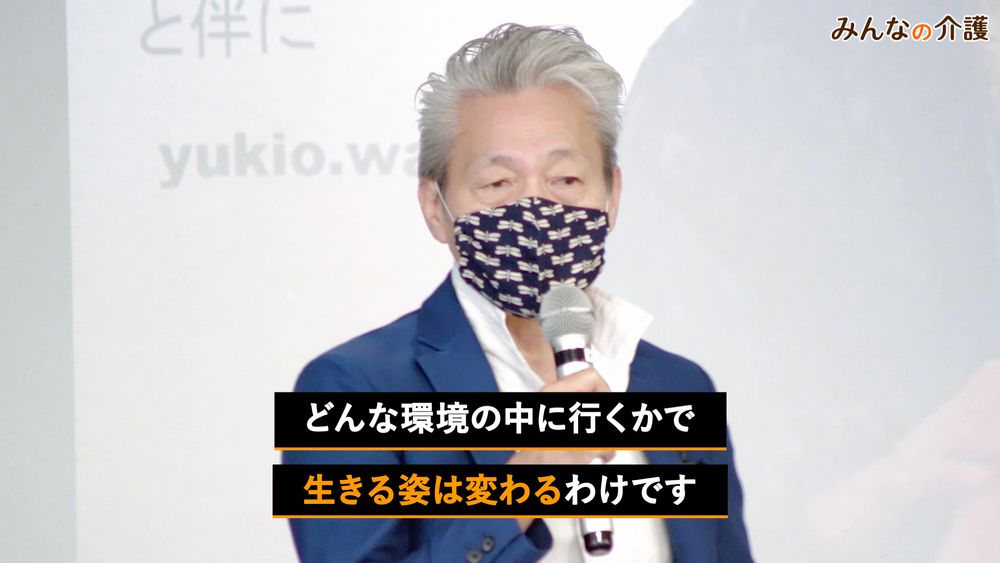
つまり、“周り”がどういう状態にあるかで、生きる姿が変わるんです。
“住民の皆さん”の受け止めによって暮らしの姿は変わる
例えば、皆さんの地域は月曜日と木曜日がゴミ出し日だとします。
今の皆さんはちゃんと月曜日と木曜日に出せてると思うんですよ。
だけど、脳に病気が起こると、ゴミ出し日を覚えていたとしても、曜日を間違えてゴミを出してしまうわけです。
皆さんのご近所に、そういう「和田さん」という方が住んでいるとしますね。
和田さんは火曜日であるにもかかわらず「今日は月曜日だ」と思ってゴミを出しに行きました。
そこでご近所にいる皆さんが「ダメダメ!お爺ちゃん今日は違うわよ!捨てちゃダメよ!」と止めたとします。
こうなると、その方の中では月曜日なので、とても暮らしにくくなります。
もし皆さんが「あのお爺ちゃん間違えてるわね…まぁ良いか!」とゴミをそっと持ち帰って、それを木曜日に出してくだされば、その方にとっての月曜日は成立しますから、生きづらさはないわけです。
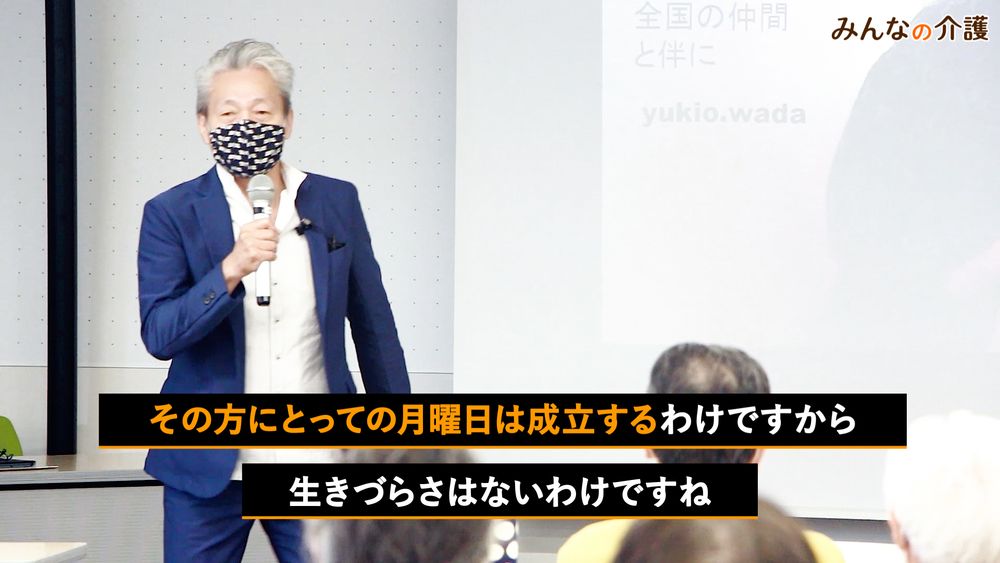
つまり、どんな環境の中にいるかで、暮らしの姿が変わるんです。
認知症の方が生活の中で起こす間違いは脳の病気によって起こるんですが、大切なのは環境要因である“住民の皆さん”です。
皆さんの受け止めがなければ暮らしにくいし、受け止めがあれば「暮らしてても良いかな」って思える状況になるということをぜひ忘れないでいただきたいなと思います。




