認知症に対しては、他人の関係で付き合う
(町永)和田さんは家族からの相談も受けていると思うので、ちょっと具体的に聞いても良いですか?
和田さんは「暮らしの支障を取り除く」と言いますが、家族や身近な人は、認知症の方の「できないこと」がどうしても目につきますよね。
できないことをなんとかできるようにしたいっていう気持ちはわかるんです。
一方で、よく図式的に言われる「できていることが見えなくなってしまう」状態ですが、このあたりはどうしたら良いんですかね?
(和田)家族はね、できない方が良い。
(町永)ほう。
(和田)家族ができるようになったら俺が失業しちゃう。
(町永・戸谷)(笑)。
(和田)というのは冗談として(笑)。家族って人間関係のなかでは極めて特殊な関係じゃないですか。
みなさんは、家族の前ではすっぽんぽんになれるわけでしょう?他人の前ではなれなくても。
特殊な関係、特別な関係だから、良い面もあれば悪い面もあると思うんですよ。
認知症に関しては、家族という関係は、悪い面が表に出やすいかな。

だからご家族は、ご本人に対してあまりきちっとしたかかわりができなくなる。
なんでこんなことを思うかというと、介護職とか医療職の人でも自分の親が認知症になったときに必ず言うんですよ。「仕事のようにうまくいかないんです!私も受け入れられなくて…」って。
その気持ち、よくわかる。だって家族だもん。
だから相談を受けるとき、いつもご家族に言ってるのは、“認知症とは他人になる”ということ。
例えば、自分の嫁さんが認知症になったとしたら、嫁さんとの関係は夫婦。これは変わらない。
だけど、認知症とは他人になる。
「認知症と」苦しい思いをしているわけです。
「嫁さんと」苦しい思いをしているわけじゃないんです。
だから、認知症とは他人の関係で付き合う。
本人のためにも家族のためにも、認知症とは何かを考え、身に着けていく
(和田)だけども、認知症とは何かを考えて、いろんなことを冷静に考えていくっていうのは、素人ではできないですね。
(町永)できませんか?
(和田)例えば、自分の家にいるのに「帰りたい!俺は家に帰るんだ!」って言ってる認知症の方に対して「なんでそんなこと言うの!ここがあんたの家やん!」って思うのは普通で。
閉じ込めようとせず、もっとメカニズムで考えて「ここにいたいと思えたら、いるんだよ」っていう解決策には、家族、素人では、いや、これを仕事にしている人でも、考えに行きつけない人がいると思うんですよ。
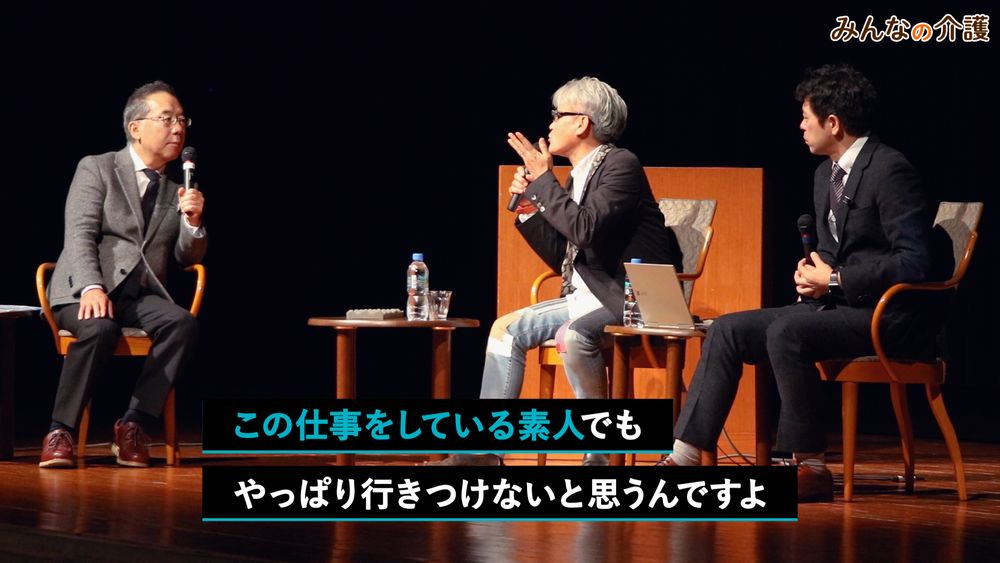
帰りたいという発言は、「ここにいるよりも家に帰る方が思いが強いんだから、当然どこかに帰ろうとするよな。だったら家に帰りたいという思いよりも、もっと強い理由がここにあれば良い」という当たり前の理屈なんですけども。
そういう考え方を身に着けていくことで、本人にとっても環境として齟齬が起きないし、家族にとっても齟齬が起きないと思うんですよ。
(福祉ジャーナリスト:町永俊雄氏の解説)
今回の和田さんは、特に難しい話をされているので、少しずつ言葉をかみ砕きながら、解説していきたいと思います。
帰りたいという発言は、「ここにいるよりも家に帰る方が思いが強いんだから、当然どこかに帰ろうとするよな。
だったら家に帰りたいという思いよりも、もっと強い理由がここにあれば良い」という当たり前の理屈なんですけども。
この和田さんの発言の中にある「当たり前の理屈」の部分です。
これはなかなか難しいところで、和田さんの言う「帰宅願望」というのは、単に家に帰りたいということを指しているわけではありません。
「今いる“ここ”が、本人にとって“不適合”であるという理屈が、家族にはわからない。
しかし、その理屈をわかろうとするところから、本人の思いを理解することに繋がる」というロジックです。
そこからさらに、和田さんは大切な視点を提示しています。
なぜ認知症の方が「帰りたい」と言うのか。
それは「“ここ”よりも、帰ろうとしている先の方が、本人の存在において意味が重い」ことを意味しています。
つまり、本質的な対応をするには、本人にとって“ここ”にいる意味を見出すことができる「もっと強い理由」が求められることになります。
和田さんの発言は「そのような関係性、ケアのあり方が成立しているのか」という問いかけで、「それを目指す理屈を身につけよ」と話しているわけです。
ケアや家族の関係性の根本的な問い直しを言っているのですね。
この言葉を入口として、「なんだろうな」と考えてもらうきっかけにしてもらえればと思います。




