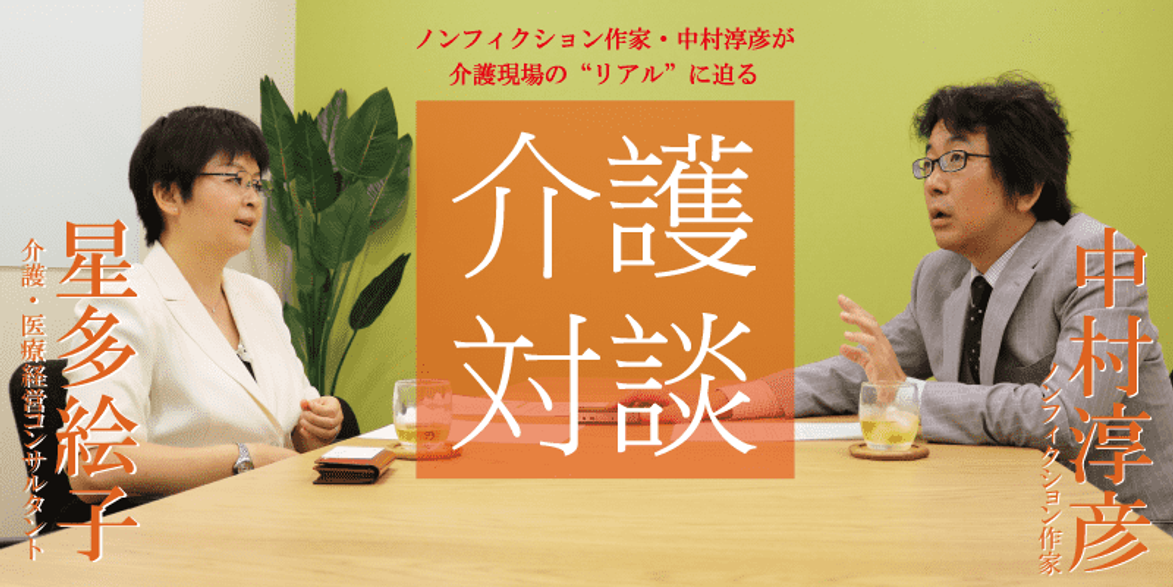星多絵子
星多絵子 中村淳彦
中村淳彦取材・文/中村淳彦 撮影/編集部
医療介護は病院や施設で面倒を見るのではなく、在宅へという流れがある(星)
星さんは中小企業診断士で、医療介護福祉に特化した経営コンサルタントをされています。ブログでは来年度の診療報酬、介護報酬のダブル改定がかなり厳しくなることを繰り返し書かれています。やっぱり前代未聞の厳冬となる雰囲気ですよね。
 中村
中村 星
星厚生労働省は2025年問題を解決するため、躍起になっています。医療介護福祉を含んだ社会保障費をなんとか抑えたい、という意向があります。だから医療介護も含めて、費用を抑えようということが大前提の議論が進んでいます。大きく言えば、医療介護は病院や施設で面倒を見るのではなく、在宅へという流れがあります。
2025年問題は人が足りないことばかりがクローズアップされていますが、もう時間切れ直前となって制度縮小が一番の目的になっているわけですね。
 中村
中村 星
星そうです。2025年問題をなんとかしたいということで、次の2018年の改定が医療介護の同時改定で、一気に大きく転換したい意向がある。高齢者はなるべく在宅で過ごしてもらって医療と介護の隔たりをなくし、診療報酬だけでなく、介護報酬もスマートにさせたいわけです。
介護報酬をスマートにさせたいことが前提となる次改定の内容は、社会保障審議会で議論中です。具体的には、どういう状況なのでしょう。
 中村
中村 星
星介護報酬を決めるにあたって、今の報酬でいいのかということを厚労省が調査しています。毎年、介護事業経営概況調査を行う。その調査結果をもとにして昨年度の決算で特養は前年度比マイナスとか、居宅介護支援は一部がマイナスとか実態を把握する。前年度比の収支差が指標の一つになっています。収支差をもとにして介護報酬を決めていくので、この調査で利益を出しすぎている報告をすると、介護報酬はどんどん削られていきます。
平成27年度の収支差率のみを眺めていると、プラスになっているのは福祉用具、居宅介護支援、小規模多機能、定期巡回訪問介護だけ。軒並み利益を下げている上に、どのサービスもたいして儲かっていません。生かさず殺さずのギリギリを探っているってことですか。まあ、さらなる削減が大前提にあるのだから、そうなりますよね。
 中村
中村 星
星ずっと介護事業者は増えている。厚労省はそれは良いことと思っていない。介護事業を行うのであっても、効率的でサービスの質のよいところを残したい。そういう報酬体系を目指しています。例えばデイサービスでもレクレーションをたくさん行って、介護状態の改善がみられる。その能力がある事業所は残したい。反対にただお預かりし、一日を過ごしてお返しするところは、よく思っていません。それは報酬に反映してくるでしょう。
状態がよくないことを、そのままにしておくことが問題視されている(星)
2015年の前回改定で小規模デイは思惑通りに潰れている最中です。今度はレスパイト型のサービスが厳しいことになると。高齢者の状態をよくする自立支援介護が言われていますが、例えばデイサービスは、高齢者のライザップみたいになるってことですか。それは、ちょっと難しいんじゃないかと思いますね。
 中村
中村 星
星難しいことではあるけど、やっているところはあります。先日見学したところは、デイサービス内で疑似通貨を発行して、高齢者が自分自身でデイのプログラムを決める。疑似通貨は映画鑑賞とかカラオケに使えて、逆にカラダや頭を使うプログラムをやると疑似通貨がもらえる、そういうシステムでした。面白いと思いました。
遊ぶためにカラダを動かすみたいな仕組みですか。それはすごいですね。介護保険を使うためには、改善を目指すことが前提という状況になるわけですね。逆に状態がよくできないところは、極端にいうと潰れてもらうみたいになる。そうなると入試みたいに利用者を選ぶし、ちょっと想像がつかないですね。
 中村
中村 星
星状態がよくないことを、そのままにしておくことが問題視されています。どうすればいいかをケアマネにフィードバックできる体制や、訪問看護など他の業種と連携していい状態を目指すことが必要になってきます。これからは一つの事業所で抱え込まないという対応が求められるようになりますね。
レスパイトがなくなるわけですか。今まで高齢者に合わせて、ゆったりとした普通の生活を提供するみたいなことが一般的だったかと思いますが、大きな変革ですね。前回の小規模デイの報酬減で知りましたが、ギリギリ運営できないくらいまで報酬を下げて潰れるのを待つみたいなやり方なんですよね。
 中村
中村 星
星レスパイト型のデイサービスを、あからさまに廃止すると反発がある。だから介護報酬の削減で絞めつけていくわけです。国の方針にあわせてこういうケアをすると明確に打ち出せる事業所や、利用者さんに生きる意欲みたいなものを持たせることができれば生き残れるのでしょうけど。
うーん。厚労省とか自治体は高齢者の生きる意欲を出させるとか、簡単にいうけど、それは至難の業ですよ。エネルギッシュで才能がある介護職でできる人もいるかもしれないけど、そんな人は特別ですよね。だいたい生きる意欲とか個人の気持ちだし、他人がどうこうできないですよ。
 中村
中村これからの介護はただ預かるだけでは厳しくなる(星)
 星
星うちの亡くなった祖母は骨折して、リハビリがつらくて仕方がなかったんです。大腿骨頚部骨折をして、リハビリが嫌でやる気をなくした。それで、そのまま寝たきりになって施設という流れでした。自分からやる気をなくすと、本当にどんどんと状態は悪化する。老化が進んでしまう。その老化が進んでしまうところを、「いいですよ」って是認するのではなく、なるべく奮起させて悪化を防ごうという意図があるのだと思います。
介護報酬で誘導して強引に健康寿命を延ばそうという考えですね。人はだんだん状態が悪くなって死ぬので、自然に逆らうようですんなり理解できないですが。
 中村
中村 星
星カラダが悪くなっていくのは仕方ないけど、心の状態ですよね。祖母はそれまで元気に働いて田畑を耕して家を守っていた。気丈な人だった。けど、リハビリが嫌になった途端にガタガタって崩れた。あんな元気で気丈だった人が、どうしてそんなことになったのかなって。介護報酬はあくまでも数字にすぎませんけど、国が介護職にそういうフォローを求めているってことでしょうね。だから、これからの介護はただ預かるだけでは厳しくなる、最悪成り立たなくなることも考えられます
けっこう多くの介護職は高齢者に生きる意欲を与えるどころか、自分自身に生きる意欲がない人が多い。諦めきっているみたいな。自分に生きる意欲がないのに、他人に生きる意欲を与えなさいって言われてもなぁ。机上の空論に聞こえてしまいます。
 中村
中村 星
星介護職の方がどうして生きる意欲をなくしているのかってところですけど、離職の大きな理由は経営者と価値観が違うこと。経営者や上司とトラブルになって辞めるみたいなケースもある。お給料だけではないのですね。
介護保険で株式会社をどんどん入れたので、当然営利主義になってくる。現場の想いと営利主義がかみ合わなくて、もう職員が働く意欲をなくしてみたいな流れは極めて一般的な人間関係の破綻ですよね。
 中村
中村 星
星最初のうちは高齢者の介護を頑張ろうと思って入ってきても、経営者や管理層との想いの相違でやる気がなくなってしまう。それで離職となってしまう。
介護職と経営者や管理層の人間関係の破綻は、いろんなケースがあるけど、どっちも悪い。介護職は搾取されているみたいなことを言いがちだし、経営層は儲け優先でなるべく人を配置したくないみたいな。前回改定から介護報酬の締めつけが始まって、経営者も儲かっていない。搾取しているのは経営者ではなく、制度じゃないですか。文句をいう相手が違うし、歪だなといつも思います。
 中村
中村 星
星介護報酬そのものも全体的に低くなっているけど、経営者は儲からない中でもなんとか利益を出そうとするので、人件費の削減をしようとする。そこも介護職の意欲を落とさせるポイントになってしまっていますね。人件費率は平成27年調査で老健59.6パーセント、特養で63.8パーセント、訪問介護は75.2パーセントですよ。
ちゃんと出ているじゃないですか。経営者が人件費を下げて搾取する時代は終わっているってことですね。逆に人件費率をもっと上げろというのは酷じゃないですか。
 中村
中村 星
星ある程度は出していますね。人件費率にはお給料だけではなく、法定福利なども含めて人件費になっている。手取りの給与が少ないっていうのもあって不満になっているのでしょうね。やっぱり離職が酷いのは営利主義がすごくて、過剰なノルマを課したり、現場の人の話を一切聞かない介護未経験の事業所ですね。
事業所の経営や運営には、経営者や管理者の人柄まで問われる(星)
介護を知らない株式会社の社長が現場の人に反感を持たれるのは、もう定番です。需要に群がって介護のことはわからないことだらけで、数字と利益だけの倫理を職員に押しつけがちで、それだと関係は破綻しますよね。でも、なにも知らない人にどんどん認可を下ろすことがまずいわけで、もう、全部制度の問題に聞こえる。
 中村
中村 星
星病院でしたら医師が医療法人の理事長とか。自治体病院でも首長が経営者で、現場監督は医師になっています。介護の場合は経営者に国家資格が求められないいところは、確かに問題かなと思いますね。様々な法人の相談に乗っていますが、経営者が自ら研修にでたり、職員のミーティングに参加したり。介護を理解しようという姿勢を見せながら、福利厚生がちゃんとしているところは、離職も少なく、うまくいっていますよ。
経営者自身は素人でも介護に興味があり、マネジメントがうまく、人柄がいいってことでしょうね。人の気持ちを理解しようとする人は、介護職に好かれます。介護はつくづく人が辞めなければ、うまくいく事業ですよね。逆に離職が高いと、それだけでダメです。
 中村
中村 星
星介護はさらにどんどんと厳しくなるので、事業所の経営や運営には、経営者や管理者の人柄まで問われますね。さらに外国人の方も入ってくるわけですし、本当に難しい時代になりました。
ありがとうございました。後半も引き続き、来年度の診療報酬介護報酬の同時改定の話をお願いします。
 中村
中村