 大津秀一
大津秀一 中村淳彦
中村淳彦取材・文/中村淳彦 撮影/編集部
終末期医療の難しさは、本人が意思表示できないケースが多いこと(大津)
中村 僕は介護現場で働いて、初めて老いとか死について考えるようになりました。小さな施設だったので何人も見たわけではないですが、認知症終末期の高齢者に家族が熱心に延命治療をして、胃ろうで、こうまでして生きて意味があるの?みたいな疑問を持ったことがあります。
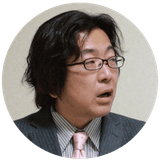 中村
中村 大津
大津大津 若い医師には同じような意見の人は多くて、その治療にどういう意味があるかを事前に十分考える習慣がだいぶ育っています。明るい未来が見えるなら、もちろんしっかり治療したほうがいい。けれども苦痛だけ増えてしまう可能性が高い場合は、積極的には延命的な治療を行わないという意見ですね。
中村 主治医の先生の考え方によっても変わってきますよね。命に関わることなので一般化できないし、本当に難しい問題だと思います。それと、介護現場の人間は基本的に医療のことはそんな詳しくありません。医療側の商売的な理由で延命させられているんじゃないかみたいな話になることもあります。
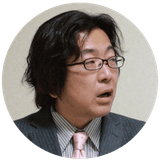 中村
中村 大津
大津大津 いや、終末期の医療を商売で勧めるようなことはないですね。そういう意見も出てくるから根深い問題ですが、基本的には善意です。善意で命を延ばしてあげたいとか、命を延ばさないといけないとか、昔はそういう考え方が一般的でした。命の長さを守ることがすごく重要でした。でも最近は長さ一辺倒ではなくて、生活の質が保たれるかというところまで考えながら、最善の判断をするようにはなっていますね。
中村 最善の判断というのは、本人と家族と担当医が三者で話して決めるのでしょうか。
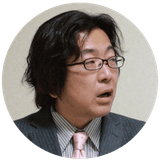 中村
中村 大津
大津大津 原則はそうです。ただ終末期医療の難しいところは、本人が意思表示できないケースが多い。そうなると本当に難しい。以前、何度か経験したのですが、本人が判断できないので胃ろうを作ってくださいと、介護施設から依頼されたこともありました。どうでしょうか判断してくださいという依頼ならいいですけれども、作ってくださいという依頼だったので困りました。一方で、本人の意思は明確ではありませんでした。
中村 キーパーソンが不在の単身高齢者は増えています。これから終末期医療の重大な局面に介護施設がかかわってくる、みたいなケースも増えるでしょうね。
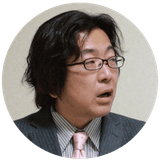 中村
中村 大津
大津大津 機能が回復する望みは少なかったし、たとえ介護施設が望んでも、その方に胃ろうを作ってもメリットは少ないだろうと判断して、口から食べるほうが本人の生活の質にもいいと判断したこともありますよね
どういう終末期を送りたいか、家族と意思を共有しておくことが大切(大津)
中村 介護をしていると、普通に巡り合うのは高齢者が突然食べることができなくなることです。遂に寿命が迫ってきたかと思っていました。
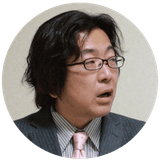 中村
中村 大津
大津大津 嚥下の機能が突出して落ちてしまった場合、胃ろうによって回復するケースは確かにあります。ただ全身が衰弱した結果として、複雑に筋肉を使う嚥下が使えなくなった場合は、ちょっと栄養を入れたくらいでは回復しないです。医師によるその見極めは重要になってきますね。例えば脳梗塞の方だと嚥下だけが悪いという場合がある。そういう状態なら胃ろうを活用して、嚥下リハビリすることによって機能回復することもあります。
中村 脳梗塞などの原因があるケースと、老衰や認知症などのケースでは対処が全然違ってくるということですね。胃ろうを入れても意味がないなら、入れないほうが誰のためにもいいですね。
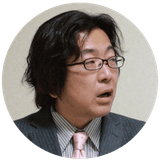 中村
中村 大津
大津大津 老衰や認知症の終末期で食べられなくなったケースだと、栄養を入れたとしてもそれが活用されません。衰弱は止まらないのです。そういう状態の方に胃ろうを作るのは、問題がありますよね。この方はこうだからたぶん治療したほうが回復する可能性があるという、回復の可能性の評価は必要です。
中村 現在の医療は進んでいて、なんでもできるというイメージがありましたが、人間の寿命は寿命ですからね。無理に延ばしても、当然生活の質が保たれるわけでないと。
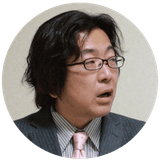 中村
中村 大津
大津大津 大切なのは自分の意思を表示して、それを家族と共有し、自分自身がどういう終末期を送りたいかということです。自分自身で判断できないことが大半で、家族が代わりに決断するわけです。仕方がないことですが、本人の意思はどうなのかがわからないと、結局、なにが正解なのかがよりわからずに難しくなってしまいます。
中村 生きている以上、終末期は全員に起こること。それに医療は進んでいる。自分はどの段階で死ぬかを決めることができるし、自分で決めなくはいけないわけですね。
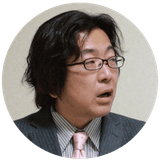 中村
中村 大津
大津大津 誰しも最後の最後は栄養が摂れなくなります。だから胃ろうなどの問題は、必ず起きて来る可能性があります。一方、ガンの場合は最後の機能低下が一気にきますので、胃ろうを作るか否かなどが問題となることは多くありません。
中村 そうか、ガンのほうが終末期は短期間なわけですね。逆に老衰や認知症のほうが長期間に及んで、選択によってはつらいケースになることもあると。
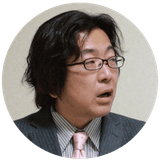 中村
中村 大津
大津大津 そうです。ガンならば、ホスピス緩和ケア病棟にも入ることができますので、ガンは恵まれているという人もいるくらいです。ガンと比べると、認知症や老衰のほうが経過は長い。例えば胃ろうが入って何年もというのはガンではあまりないことです。結局、認知症や老衰の難しさは栄養をどうするのか、そのときに本人が意思表示できる状態にない可能性が高いというのが、終末期の大きな問題になっていますね。
本人にとって無駄な治療、本人にとって意味のない治療は減らしたほうがいい(大津)
中村 「大往生したければ医療と関わるな」「どうせ死ぬならガンがいい」など、ガンになったら医療に頼らないことを薦める本も流行りました。
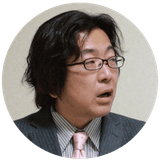 中村
中村 大津
大津大津 緩和ケアも進歩しましたし、ガンは比較的自分の意思が反映できる病気なんですね。ガンの患者さんは、自分はこうしたいと自分の意思を言える。しかし、例えば80代後半の重度の認知症の方が食べられなくなったとき、「どうしたいですか?」と聞いても、まず答えられない。
中村 家族や医師など、本人以外が本人の意思を類推して治療をしなくてはいけないんですね。数年、命が延びるかもしれないけれど、その延びた命は本人にとって意味があることなのかわからないわけですね。
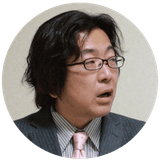 中村
中村 大津
大津大津 高齢者は非常に増えているし、多くの方に終末期の問題を知ってもらって、健康なうちに自分の意思を伝えたり、共有することが必要ですね。本人にとって無駄な治療、本人にとって意味のない治療は減らしたほうがいいと思います。
中村 今は社会保障費のことも問題ですし。医療も介護も現在のまま維持継続はできないと、もう誰もがわかっています。無駄な治療を減らすことで医療費削減、みたいな効果はあるのでしょうか。
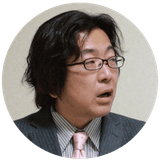 中村
中村 大津
大津大津 ちょっと、でしょうね。今、医療費は増えていますけど、そのうち多くの部分は医療の進歩に伴う費用と言われています。結局、高齢者医療は医療費の上乗せ分の一部でしかない、という考え方があります。高額な薬とか新しい薬・技術が、医療費上昇の主な部分とも言われています。医療費を削減することとは別に、個々にとって良い選択がされるようにという支援は重要だと考えます。
中村 薬価が高額すぎて問題になった抗がん剤のオプジーボみたいな薬のことですね。一回の薬価が130万円とか。すごい金額で、投与する患者に対する費用対効果が議論されはじめたり。
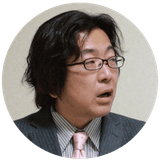 中村
中村 大津
大津大津 医療技術が進歩すると新しい薬が出てくる。それはときとして高額です。医療の進歩によって医療費は増大しているわけです。だから一般の人が思うほど、高齢者の影響は受けていないのではないかと思いますね。高齢者の方々は国の医療費に迷惑をかけるから、という考え方はしなくてもいいと思いますね。あくまで自分にとってどうかということで考えてほしいです。
自分の死は誰も経験したことがないのだから、準備が必要(大津)
中村 人間は誰もが死ぬ。超高齢社会になって財政的にもひっ迫している。一方で医療も緩和医療も進んでいる。これからは本人や家族は死に対して、どういうことを考えていけばいいのでしょうか。死に対してネガティブな意識がある人が多いことから、様々な歪みが生まれているように感じます。
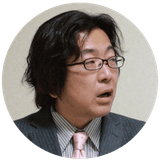 中村
中村 大津
大津大津 自身の死は誰も経験したことがないですから、準備万端っていうのも変な話自ではありますよね。僕は終末期の方を2000人くらい診てきましたが、だいたいみなさん準備万端ではないです。大事なのは、自分自身が終末期をどうしたいのか決めておくこと、あるいは決めたことを家族とちゃんと話し合うことです。なぜかというと、本人と家族の意思は大抵違ってきますから。
中村 本人はもう十分と思っていても、家族はもっと長生きしてもらいたいと。人間は必ず死ぬという意識を持っていないと、「長生きは無条件にいいこと」みたいな価値観になってしまう。平穏な家庭ほどそうなりますよね。
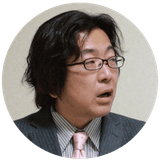 中村
中村 大津
大津大津 そういうすれ違いは本当に多くて、自分は穏やかに死にたいと思っていても、家族がやっぱり一分一秒でも長く生きてもらいたいということもあります。以前も、ご本人は『もう、覚悟していますから穏やかに死なせてください』と訴えても、60代の娘さんが『先生、この人の言うことを聞く必要がないです』みたいなことがありました。娘さんはお父さんを尊敬していた。長く生きてもらいたかったんです。本当に難しいですよ。
中村 本人と家族で考えが一致すれば最善だけど、まあ、そうじゃないのが普通でしょうね。揉めるのは仕方ないのかもしれません。
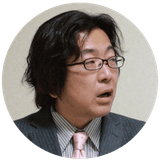 中村
中村 大津
大津大津 そのためにこそ、我々のような医療者がいるのだし、上手に使ってもらいたいですね。結局、その父娘のケースは、両者の話を十分聞いたうえで、「娘さんの想いはわかるけど、やっぱりご本人の意向がある。それに沿うのがご本人にとって一番良いことなのではないですか」ということを伝えながら、娘さんの気持ちが変わっていくのを待ちました。
中村 大津先生の著書に、全身管まみれになって苦しい終末期を送った方の痛々しい話がありました。限界まで延命させてくださいという家族の意向は、本人にとっては迷惑なケースもたくさんあるのですね。
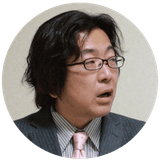 中村
中村 大津
大津大津 前編でも話しましたが、一度はじめた治療を途中で中止するのはときとして難しいです。元気なうちから、自分が食べられなくなったとしたらどこまで治療してほしいか、よく話し合ったほうがいいでしょう。自身は意思表示ができない状態で、かつ、家族は長生きしてほしく、できることは全てやってくださいと希望されているならば、自分の希望と反する終末期になる可能性はあります。
中村 人はみな死にます。では、これから高齢者になる方々は自分の死と向き合って、自分はどういう終末期を送りたいのか決めなくてはならないですね。
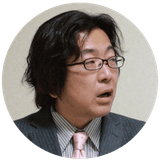 中村
中村 大津
大津大津 さらに踏み込んで、こういう治療は絶対にやってもらいたくないとか、自分の意思を家族にはっきり伝えておくべきです。例えば自分の口から食べることができなくなったら胃瘻はしないとか。できれば、紙に書いておくのがいいでしょうね。紙に書いて、ちゃんと話し合いもする、それが大切です。
中村 最後、どう死ぬかを自分で決めるということは、本当に重要ですね。先生が取り組む緩和ケアもあるし、自分がしっかりすれば終末期は安心だということがわかりました。ありがとうございました。
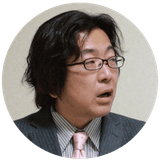 中村
中村




